おおつき花図鑑
草花の名前と花の時期を知れば、もっと楽しい!大月町で出会える「牧野博士ゆかりの植物」
海辺の植物編
緑に恵まれた大月町では里地里山だけでなく海のすぐそばにまで植物たちの豊かな世界が広がっています。海辺という厳しい環境に生きる海岸植物が咲かせる花はどれも美しく、風景をより見ごたえのあるものにしています。このような花と雄大な海辺の風景のコラボレーションが楽しめるというのも大月町で植物観察を行う大きな魅力のひとつとなっています。同じ場所でも季節によって異なる花を見ることができるので、何度も訪れて楽しむことができます。
※植物の分類は APG 分類体系に従いました。
※花の時期は目安です。
※花の時期は目安です。
大月町で採集した標本に基づいて新種記載したもの
牧野博士ゆかりの植物

ハマダイコン
アブラナ科
花の時期:3 ~ 5 月
北海道から九州の海岸の砂地や河口付近 に生息する越年草。春に薄紅色の花を付け、海岸に彩りを添えます。全草に辛みがあり、花や若芽、さや、根などを春に採取して薬味などとして利用できます。


タチツボスミレ
スミレ科
花の時期:4 ~ 5 月
全国に分布し、海岸から山地の日当たりのよい林縁などに普通に見られる多年草。町内で最もよく目にするスミレの仲間の一つ。葉は薄くハート形で花は薄紫色で葉のつけ根に 1輪ずつ付きます。



コバノタツナミ
シソ科
花の時期:4 ~ 6 月
関東地方以西に生息するタツナミソウのの変種。海岸近くの林縁に群生します。短い毛が生えていることからビロードタツナミとも呼ばれます。春に青紫色の花が集まった花穂(かすい)をつけます。

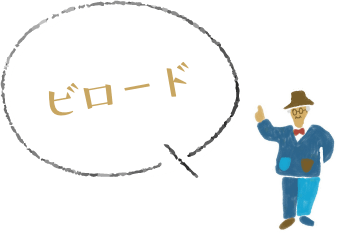
ハマエンドウ
マメ科
花の時期:4 ~ 7 月
日本各地の海岸に生息する多年生の海浜植物。砂浜に多く、礫浜にも出現します。春に濃紫色の美しい花を咲かせます。春に若芽や若葉を収穫して食べることができます。花も食用になります。


ハマボッス
サクラソウ科
花の時期:5 ~ 6 月
北海道から沖縄まで広く分布する二年草で海岸の岩場に生息します。白い花をたくさん咲かせた様子を馬の毛などを束ねて柄を付けた法具、「払子(ほっす)」に見立て、和名がつけられました。




タイトゴメ
ベンケイソウ科
花の時期:5 ~ 7 月
本州から九州に分布する多肉性の多年草。海岸の岩場に生息し、初夏に黄色い花を咲かせます。たいとごめは、大月町の方言で上等ではない外国米(大唐米)のこと。柏島で採集・記載されました。


ハマヒルガオ
ヒルガオ科
花の時期:5 ~ 8 月
世界に広く分布する海浜植物で日本では北海道から九州に生息します。ほふく状に茎をのばし、群落をつくります。初夏から夏にかけて美しい薄紅色のアサガオに似た花を咲かせます。


ハマナデシコ
ナデシコ科
花の時期:6 ~ 11 月
本州から沖縄の海岸に生息する多年草です。太平洋岸の岩場や砂浜に多くみられます。葉は厚くてつやつやしています。花期が比較的長く、春から秋にかけて紅紫色の花をたくさん咲かせます。


ハマゴウ
シソ科
花の時期:7 ~ 9 月
北海道をのぞく全国の海岸に生息する常緑低木。砂浜や礫浜に生えます。夏から秋に青紫色の花を咲かせ、実は秋に黒く熟します。芳香があり、お香などに用いられます。


ハマオモト
ヒガンバナ科
花の時期:7 ~ 9 月
関東南部より西の海岸に生息する球根性多年草。ハマユウとも呼ばれます。夏に白い花をつけ、秋になると果実が熟します。果実は乾燥に強く、水に浮く性質があり、海流によって遠くに運ばれます。




オオハマグルマ
キク科
花の時期:6 ~ 12 月
紀伊半島以西に生息するネコノシタの変種。海岸の砂地や礫地に茎を這わせて延びる多年草です。ネコノシタと同様に葉がざらざらしています。頭花は 1-3 個付きます。大月町柏島がタイプ産地です。



ハマアザミ
キク科
花の時期:7 ~ 11 月
伊豆半島以西の太平洋岸に生息するアザミの仲間。根が食用になり、ハマゴボウとも呼ばれます。春に採れる若葉を炒め物やてんぷらにして食べます。夏から冬にかけて紫色の可愛い花を咲かせます。

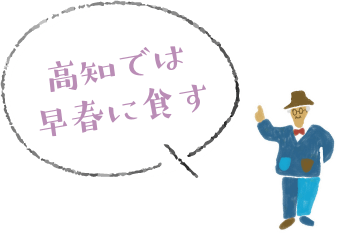

ハマカンゾウ
ワスレグサ科
花の時期:8 ~ 10 月
関東地方以西の暖地の海岸に生息する多年草。日当たりのよい崖地・急傾斜地などに群生します。晩夏から秋に橙赤色のユリの仲間に似た花を咲かせます。この花は朝開いて 1 日でしぼみます。



ヤマヒヨドリバナ
キク科
花の時期:9~11月
四国、九州から沖縄の山地に生息する多年草。多数の白い花が茎の先に集まって咲きます。海を越えて旅をする蝶、アサギマダラの吸蜜植物で、有毒成分(アルカロイド)を多く含んでいます。


ツワブキ
キク科
花の時期:10 ~ 12 月
本州中部以西に分布し、海岸近くの林床や林縁に多い常緑多年草。葉は厚く、光沢があります。冬を彩る黄色い花には海を越えて旅をする蝶、アサギマダラが吸蜜に訪れます。葉柄は食用とします。




ソナレノギク
キク科
花の時期:10 ~ 11 月
四国南西部と九州南東部の海岸に生息する二年草。ヤマジノギクの海岸型で大月町柏島がタイプ産地となっています。「そなれ(磯馴)」とは海岸の環境に適応した植物を表す言葉です。


アシズリノジギク
キク科
花の時期:10 ~ 12 月
高知県足摺岬から愛媛県佐多岬までの海岸に多く見られるノジギクの変種。葉の裏や縁に毛が密生し、白く縁取られているように見えます。晩秋にかけて美しい白い花をたくさん咲かせます。


大月町で出会える希少な植物たち 寄生植物・菌従属栄養植物の仲間

ツチトリモチ

ヤッコソウ

ギンリョウソウ
寄生植物はほかの植物の根などに寄生し、栄養分を吸い取ってくらしている植物です。町内ではハイノキやクロキに寄生するツチトリモチ、スダジイやツブラジイ(コジイ)に寄生するヤッコソウなどを見ることができます。菌従属栄養植物は落ち葉や枯れ木を分解する腐朽菌(きのこの仲間)から栄養を得て生きている植物で、町内にはその代表であるギンリョウソウが分布しています。
※ここに挙げた植物には絶滅危惧種等の指定を受けているものも含まれます。採集は控えましょう。





